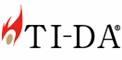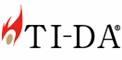

ビジネス戦略を戦国時代に見て

昔のブログにはよく書いていたことがあります。
それは歴史ネタです。
今回再スタートしてまだ4ヶ月目のこのブログには、まだ書いていなかった(^^;
僕はビジネスストラテジー(戦略)を考える時にふと過去の歴史が思い浮かびます。
日本の戦国時代や、三国志時代の中国、また古代ローマ等などと。
そこで今回は日本の戦国時代のお話です。
この国は大陸と比べるとこんな小さな島国です。その島の中で応仁の乱以降100年間も小国に分かれて戦争、戦略(strategy)と戦術(tactics)や兵站(Logistics)を続けてきた歴史があります。これはある意味凄い歴史です。
これらの技術の進化や運営、これは現在の企業戦略にも類似する事が多々あるのではないかと、色々想像してしまうのですね。
例えると有名どころでは、甲斐の「武田信玄」。今の山梨県、長野県周辺に広大な版図を築いた戦国大名です。ですが、彼の領土は地図上で見ると広大なのですが、大半は山岳地帯で農耕には不向きな地域で、実質石高は120万石以下と言われています。(1万石=約400名の雇用能力)これに比べ隣国の北条家は200万石以上の国力はあります。そして北の上杉に南の今川と割拠している環境があったのは皆さんご存知のとおりです。そんな環境の中で武田家は最大出兵能力3万で長期遠征可能な軍団が整備されているのです。
そして戦国期が終わり、豊臣秀吉の時代となりました。その安定した時代で武田家と同じ国力の大名と比較して欲しいのです。上杉家、毛利家がちょうどいい国力でしょうか。共に120~130万石前後。この時代は戦乱は無く、また検地により実質石高も上がっています。また商工業も発展し、環境的には戦国期よりは当然安定しています。その時代でようやく戦国期の同数の出兵、遠征能力を維持できるのがやっとの事で、武田家のように四方を敵国に囲まれ交易にも制限があり、石高も山間部という不利な立地で、このような軍団や国家体制を作り上げれたのは国主のカリスマや手腕なんですね。
ある意味ビジネスの戦略も同じなんですね。
ビジネスの収益が石高であり、それからの経常利益や貯蓄高も決まりますし、さじ加減で大きく変わります。そしてそれらによって次の戦略(投資)も定まってきます。現在より大きな標的(市場)を狙う場合は、それなり以上に情報収集や、人脈作り、場合によっては調略までも必要になります。まあランチェスター法則等で書かれているように、目標は自分より小さなところがベターなのですが。。
現状を維持することが精一杯な事業と、安定し資産を増やせる会社とは、中身の性質や経営者の能力が全く異なっているのだと思います。ビジネスは生き物です。リアルタイムで状況も動いています。型にこだわるのでなく、従来、既存、にとらわれる事なく前に進んでいくことが何時の時代も重要なことなのかもしれませんね。
駄文に長々とお付き合い頂きましてありがとうございました。
☆参考になったなと思った方はクリックください☆
 絶えまない変化の先に
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
絶えまない変化の先に
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ブログランキングクリックご協力ください
関連記事